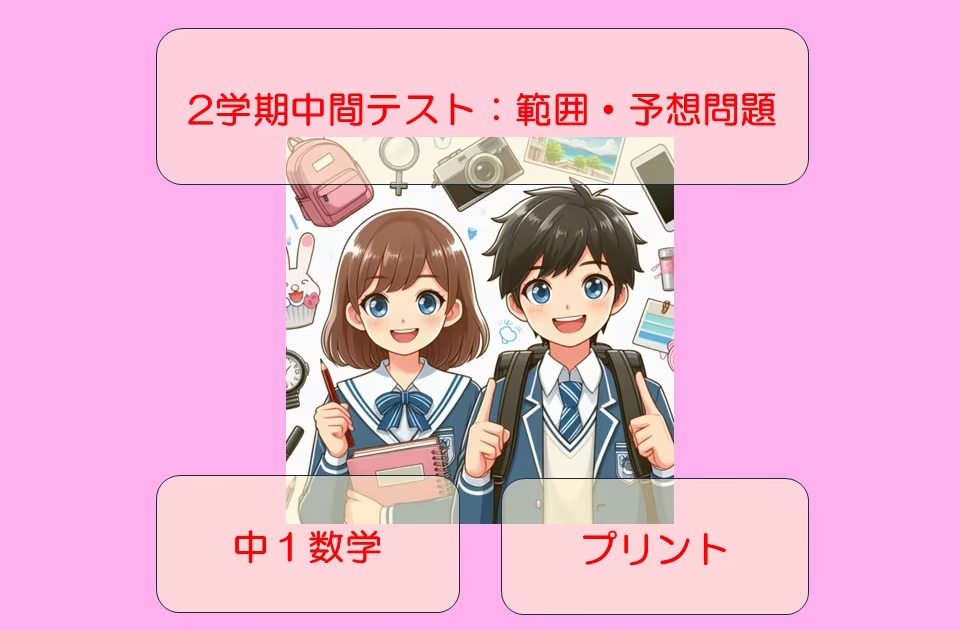みなさん、こんにちは!そろそろ、2学期の中間テストの頃ですね。
📌まず「範囲」と「予想問題」をチェック!
「中1数学の2学期中間テストって、どんな範囲が出るの?」「予想問題で対策したい!」
そんな声に応えて、この記事では2025年度の中間テスト範囲の傾向と、予想問題を使った7日間の勉強法をご紹介します。
中1数学|2学期中間テストの出題範囲(2025年版)
📌ズバリ!「文字式」と「一次方程式」を中心に!
+αで「比例」「資料の整理」?!
さて、多くの中学校では、以下の単元が中間テストに含まれる傾向があります。このなかで中心になるのが「文字式」と「一次方程式」です。「比例」「資料の整理」は進度や学校によって期末テストに回ることもあります。
つまり、みなさんの学校が示す「試験範囲:教科書p〇〇~p〇〇」が最重要。これは、ぜったいに確認してください!試験準備の第一歩です。
| 単元 | 内容 | 出題傾向 |
| 文字式 | 式の計算、項・係数、式の値 | 計算問題が中心。分数や単位の変換も注意 |
| 一次方程式 | 解法の基本、文章題 | 等式の性質や文章題が頻出 |
| 比例(導入) | 比例の意味、グラフ | グラフの読み取りや式の理解が出題されることも |
| 資料の整理(導入) | 平均、度数分布表 | 基本的な統計処理が軽く出題される場合あり |
※進度や学校によって「比例」「資料の整理」が期末テストに回ることもあります。
こちらにも「文字式の計算と応用」、「方程式」の記事があります。ご参考にしてください。
予想問題&練習プリントの活用法
それでは、中間テストの準備を始めましょう。
📌あれこれ手を広げず、集中的に繰り返し練習
そこで、以下の予想問題プリントと解き方練習プリント①②③を用意しました。みなさんの学校の試験範囲の確認をしたら、すぐに始められます。学校の試験範囲に合わせて使ってね!
🖨️プリント
予想問題プリント(1枚):実際のテスト形式に近い構成。文字式・方程式中心+比例・資料から1〜2問
練習プリント①(基礎〜応用):文字式・方程式の計算力強化+文章題
練習プリント②(+α対応):比例の理解を導入レベルで練習
練習プリント③(+α対応):データの読み方を導入レベルで練習
プリントはすべて無料です。公式LINE「中学生の道具箱」に登録後「今月のプリント」からご利用いただけます。こちらは、当サイトが運営するプリント専用のサイトです。
※QRコード読み取り、または、登録ボタンからお気軽にどうぞ。登録・解除はいつでもご自由です。

7日間スモールステップ勉強法|時間がなくても取り組める!
まず、各プリントの所要時間は25~30分です。毎日、無理なく取り組めますね。そして、厳選の基本問題→解答を繰り返すことで、各単元の「解法」が理解できます。
こちらのプリントは、すべてLINE「中学生の道具箱」内「今月のプリント」に格納されています。どの部屋にあるプリントもご利用いただけます。
プリントの使い方
では、いよいよプリントを使い、7日間で中間テストの準備をしましょう。
- 初日(1日目)に予想問題プリントに取り組む。
→今の時点での解答力を知る。タイマーを使い、時間を意識しよう! - 2日目~6日目は、練習プリント①に取り組む(②③は必要に応じて)
- 最終日(7日目)に再び予想問題プリントに取り組む。見直しも重視。
→練習の成果を知る(正答数や解答スピードの変化にも注目してね!)
| 日数 | 学習内容 | 使用プリント | 学習のポイント |
| 1日目 | 予想問題を時間を計って解く | 予想問題プリント | 「今の自分を知る日」すぐに丸つけしてみて!これがスタートの自分だよ! |
| 2日目 | 文字式の基本と計算(項・係数・加減乗除) | 練習プリント① | 「式の意味と計算のコツをつかもう」短時間集中でOK |
| 3日目 | 文字式の応用+比例の理解 | 練習プリント①+② | 「式を使って表す練習」必要なら②で「比例」もね! |
| 4日目 | 一次方程式の基本(解法の手順) | 練習プリント① | 「途中式を大切に」手順を整理してみよう |
| 5日目 | 一次方程式の文章題+資料の整理(基本) | 練習プリント①+③ | 「問題文から式を立てる練習」必要なら③で「用語の意味」と「データを読む練習」も。 |
| 6日目 | 方程式のまとめ+苦手チェック | 練習プリント① | 「できたところに〇をつけよう」解答用紙のチェック欄を使い、達成感を意識しよう |
| 7日目 | 予想問題をもう一度解く+見直し | 予想問題プリント | 「前回との違いを見てみよう」時間いっぱいまで使い「見直し」してね!今の自分は、初日とはどう変わった? |
🌱保護者の方へ:声かけのヒント
中1では、試験準備自体がよくわからないお子さんが多いです。ですから、保護者の方による「タイミングのよい声かけ」がまだまだ必要です。
とはいえ、本人に「いつまでも小学生扱い…」と思われても困ります。もしかすると、「プリント印刷や整理を手伝いがてら、」が自然な声掛けのタイミングなのかもしれません。
- 「今日はどこまでやった?」と聞くより、「〇つけたところ、見せてくれる?」と促す。
→お子さんの「安心感」につながります。 - 「昨日より速く解けたね」「文章題、式が立てられてる!」など。
→お子さんが気づかないような「小さな変化」を認める。
また、小学校とは異なり中学校の試験では、「問題冊子と解答用紙」という形式が増えます。この試験の形式にも早く慣れておきたいですね。プリントは、この形式に近い形になっています。
ご家庭にプリンターがあると、お子さんの学習が一段と進めやすくなります。
最近はコンパクトで安価なモデルも多いので、学習机の横に置けるサイズのものがおすすめです。
大切な書類を保管する機会が増えますのでコピーやスキャナー機能も便利です。
まとめ|中間テストは「できる」を増やすチャンス
最後に、中学の定期テストは「予想問題当てや点数勝負」ではありません。中学生のみなさんは、つぎの「2つの知る」を意識しましょう。
2つの知る
試験前の学習で、どこがわからなかったか、どうすれば解けるようになるかを知る。
試験前の学習が、中間テストの結果にどのようにつながったかを知る。
この7日間の取り組みが、きっとみなさんの「できる」を増やしてくれるはずです。試験準備の仕方がわかったり、他の科目の勉強にも目が向いたりするといいですよね。
たくさんの「できる」のきっかけにしてくださいね!いつも応援しています。
では、また💛
学習用タイマー👉Amazonで見る(PR)